Yes, I will. written by 加古いく
「ってことで、willは分かった?」
「うん。分かった」
「じゃあ、練習問題やるわよ」
「うん」
「Will you go to school tomorrow?」
「え? え?」
速くて聞き取れなかった。
「『え』じゃないでしょ、『え』じゃ。Will you go to school tomorrow?」
ああ、学校に行くのか、って聞いてるのか。
「ああ、えーと・・・、Yes, I will.」
「へー。あんた日曜日も学校行くの?」
「え?」
「何しに行くの?」
「ごめん、」
「あたしも行った方がいい?」
分裂する使徒を倒した後も、アスカは引き続きうちに住むことになり、ぼくたちは一緒にいる時間が増えた。家に帰ると、アスカにリビングに引っ張り出されて、宿題と予習を一緒にやる。月曜日の分を土曜日のうちにやっちゃうのはアスカ流だ。日曜日は思いっきり遊びたいんだって。
テーブルの上には、ウーロン茶のペットボトルと、お菓子の入ったお皿、それに、ぼくとアスカの教科書とノートが何冊か置かれている。今、アスカは、月曜日の6時間目の英語の授業で習う予定の、「助動詞」を教えてくれている。ぼくの英語や数学、理科の教科書は、アスカがシャーペンで遠慮会釈なく書き込んだコメントだらけ。アスカのはまっさらだ。これが国語や社会だと、反対になる。
「聞き取れなかった?」
「うん・・・」
「Will・you・go・to・school・tomorrow?」
「あー、分かった。No, I will not.」
「No, I won't.」
「あそっか。No, I won't.」
「よし。今日はこの辺でいいでしょ。Any question?」
アスカがこっちを向いて訊いた。ぼくは、首を横に振った。
「No.」
「Good.」
アスカは、英語の教科書を閉じて、片付けを始めた。
「なんかさ、最近、英語の授業面白いんだよね」
「そう?」
「うん。良く分かるし」
「良かったじゃない」
「アスカのおかげだね」
「分かってんじゃないの」
アスカは、機嫌良さそうに微笑んだ。
そのアスカの顔の向こう、ベランダから見える空に、いくぶん赤みが差してきた。振り返って、棚の上の時計を確認すると、もう晩ご飯の支度をする時間だった。
「そろそろ、」
「なんか、お礼してくれないの?」
「え? えー・・・」
「なによそれー」
「いや、だって、国語とかぼくが教えてるだろ?」
「だからいつもお礼してるでしょ?」
「そうだっけ?」
「そうよ。お買い物付き合ってあげてるじゃない」
「あー・・・」
学校や、ネルフの訓練からの帰り道、アスカと一緒に晩ご飯の買い物をするようになった。今日も、午後の訓練の後、駅前のスーパーで食材を買うのに付き合ってくれた。それは、確かにそうなんだけど、たぶん、アスカの目的は、晩ご飯とおべんとのメニューに自分の好みを反映させることじゃないのかな。たまに、ぼくの好きなものとか、ネットで調べた新しいレシピを試すこともあるけど、二人で買い物するようになってから、それにはアスカの許可が要るようになってしまった。
でも、今日のような暑い日に、荷物を持って、帰りの坂道を登っていくのは、けっこうダルい。そんなときに、アスカが買い物袋を一つ持ってくれたり、アイスをおごってくれたりするのは、確かに助かってる。
「あれって、お礼のつもりだったんだ」
「そうよ。何だと思ってたの?」
そう言われても。
「あ、じゃあさ、今日の晩ご飯、おかず、何か一品、増やしてあげるよ」
「ほんと?」
「うん。何がいい?」
「お肉」
「即答だね」
「聞くだけムダってもんよ」
「でも、メインもお肉だよ?」
「そうだっけ?」
「だって、さっきスーパーでアスカがお肉がいいって言うから、豚肉買っただろ」
「あーあー。そうだったわね」
「肉と肉でいいの?」
「問題あんの?」
「いや、ないけど・・・」
「ならいいじゃない」
「アスカのリクエストじゃしょうがないか」
「なによそれ。あたしが我がまま言ってるみたいじゃないの」
「え? いや、そうじゃないよ。どうせ作るなら、アスカが喜んでくれるものの方がいいってこと」
「・・・ふーん」
アスカは、ちょっと考えてから言った。
「あたしの好みに、合わせてくれてるわけ?」
「当たり前だろ? 食べてくれなかったら困るしさ」
「そっか。当たり前なのか」
「アスカも、作ってみれば分かるよ。美味しそうに食べてもらえるとさ、ホント、うれしいから」
「あたしはムリよ」
「うん。作れって言ってるわけじゃないよ」
「・・・いつも・・・、」
「なに?」
「・・・いつも通り、美味しく作んなさいよ」
アスカは、立ち上がって、ぼくを促した。
「いいから、ほら、おしゃべりしてないでさっさとやんなさい」
今日のおかずは、豚肉の生姜焼きと鶏の唐揚げに決定した。
◇
近頃ミサトさんは、早く帰ってきて、一緒に晩ご飯を食べることが多い。でも、だからといってヒマなわけじゃないらしい。晩ご飯の後はだいたい、台所のテーブルの上に書類を広げて、何か仕事をしている。自分の部屋の机が散らかし放題・・・塞がっていて、ぼくたちがリビングを占領しちゃってるから、他に場所がないんだそうだ。
「あれー? ねえ、シンちゃん」
「はい、何ですか?」
今日もミサトさんは7時前に帰って来た。部屋着に着替えて台所のテーブルに付くなり、目を輝かせて訊いてきた。
「今日は何か、お祝い?」
「え? いえ、違いますけど・・・」
「じゃー、なんで、おかずが豪華なのー?」
「あー、えーと・・・」
「何言ってんのよ。食べ盛りが二人もいるんだから、このくらい普通でしょ?」
アスカが代わりに答えた。そうかなぁ。ドイツではそうなのかな。
「まあ、それならいいけど」
「まずかったですか?」
「んーん。オッケーよ、全然オッケー。むしろ大歓迎?」
「ほらごらんなさい。だからあんた、明日からはこのくらいやんなさいよ」
「えー、でも、けっこう予算が・・・」
ぼくはミサトさんの方をチラっと見た。
「あはは、いいわよ、そのくらい。・・・で、今日のこれ、いくらかかったの?」
「えーと・・・、サラダ350、お味噌汁400、野菜のフライ、小鉢、お漬け物・・・、鶏唐、生姜焼き、か。全部で3300円くらいですね。揚げ物、油使いますから」
「・・・あっそう」
「ごはんとビールは別です」
ミサトさんは、少し、テンションが下がったみたいだった。
◇
「あんた、ご飯食べるとき、いつもエプロン着けっぱなしよね」
「うん」
「気に入ってんの?」
そう訊いてから、アスカは、自分の小鉢に残ってた最後の烏賊と里芋にフォークを突き刺して、口に放り込んだ。
「いや、そういうわけじゃないけどさ、どうせ食べ終わったら片付けしないといけないから、いちいち外すの面倒だし」
「あー、あるほろれ」
アスカは、烏賊がなかなか噛み切れないみたいだった。
「うん。前掛け代わりにもなるしね」
「シンちゃん、食べるときこぼしたりしないじゃない」
ミサトさんが口を挟んだ。
「ええ。でも、たまたま、ってこともありますし」
すると、隣に座っているアスカが、こっちを向いて、改めてという感じでぼくの姿を上から下まで眺めて言った。
「エプロン、いつもおんなじの着けてて飽きない?」
「え? いや、別に、飽きないけど・・・」
「ここんとこ、ちょっと染みになってんじゃない」
アスカは、左手の先で、ぼくのお腹のあたりを突っついた。
「いや、だって、別に、外に着てくわけじゃないしさ・・・」
「ふーん」
「なあに? シンちゃんのエプロン、気に入らないの?」
「そういうわけじゃないけど、・・・そういうわけじゃないわよ」
食べ終わったアスカは、ウーロン茶のグラスに手を伸ばした。
「シンちゃんに買ってあげたらー? 新しいエプロン」
アスカが顔を上げて「なんであたしが、」と言うのと、ぼくが「そんな、悪いですよ」と言うのが同時だった。すると、アスカは、再びこっちを向いて、
「新しいの欲しいわけ?」
と訊いた。真面目な顔だった。
「えっと、欲しい、ってわけじゃないんだけど、もう一つあると、洗濯が楽かな・・・」
「ふーん」
「でも、なくても全然困らないよ」
「遠慮しなくったってイんじゃないのー?」
ミサトさんが、からかうように言った。
「遠慮しますよ。それでなくったって、いつも帰りに、」
アスカが、えへん、と咳払いした。あれ? 何かマズいのかな?
「なあに? アスカに何か買ってもらってんの?」
「えーっと・・・」
ぼくはアスカの方を、横目で、ちらっ、と窺った。アスカも、横目でこちらを睨みながら、グラスのウーロン茶を飲んでいる。
「ま、まあ、いいじゃないですか」
「なによう。あたし除け者?」
「あはは・・・、すみません」
「ごちそうさま」
アスカはそう言って、自分の食器を片付けて、シンクに持っていって、水を張ってくれた。
「あら。ご機嫌斜めかしら」
◇
今日は、おかずがいつもよりも豪華だったせいか、ミサトさんはいつもよりもいっぱいビールを飲んでいた。テーブルに左手で頬杖を突いて、右手に持ったビール缶に印刷されている説明を、今日初めて見たとでも言うように、眺めてる。
ミサトさんが使ってる食器を除いて洗い物が終わり、台布巾でテーブルを拭き始めたところだった。
「ねー、シンちゃーん」
少し鼻にかかった、甘えるような声で話し掛けられた。やっぱり、ちょっと酔ってるんですね。
「はい」
「アスカどう?」
「どう、って・・・、相変わらずですよ」
適当な返事が見当たらなかったので、そう答えた。
「そうじゃなくってー。一緒に暮らしてみてさ」
ミサトさんは、缶ビールから視線を外して、こっちを向いて訊いた。ぼくは、その視線から逃げるように、台布巾を漂白剤に晒しながら、答えた。
「ああ、はい。別に、普通だと思いますけど・・・」
「そー。喧嘩してない?」
「それは、ときどきはしますけど・・・」
「じゃあ、だいたい仲良くしてるんだ」
「そうですね、普段は」
「そっかー。ちきしょー、いいなー、若いってのはー」
「そ、そんなんじゃないですよ、ただ、」
「あはは、いーからいーから。お姉さんちゃんと分かってますって。そういうこと言ってんじゃないのよ」
ミサトさんは、7本目の缶ビールを、グイっ、と呷ると、テーブルの上を左の方へコロコロと転がした。金色のビール缶は、そのまま転がっていって、アスカの席の正面に林立している空き缶の山にぶつかって、止まった。
「もう一本ですか?」
「んーん。お湯割りにする」
「『魔王』ですか?」
「うん。梅干しも出して」
「はい」
「いっつも悪いわねー」
ミサトさんは、一杯約60円のシジミのお味噌汁を飲み干すと、ふう、と溜息をついて、続けた。
「シンちゃん、ほんと、明るくなったわねー」
「ぼく、暗かったですか?」
グラスに焼酎を注ぎながら、訊いた。
「まー、そうねぇ。明るいか暗いかって訊かれたら、明るいとは答え難かったかな」
「あはは、そうですか」
「アスカが来てからよね」
「そうかな・・・」
「そうよー」
「自分では、あんまり変わったって思ってないんですけど・・・」
「ふーん。まー、いーんじゃないのー?」
「はい、どうぞ」
いつものグラスに焼酎のお湯割を作って、マドラーを挿して差し出した。小皿には梅干を2つ。
「それじゃ、ぼくも下がります」
「リビング?」
「はい」
「アスカが待ってんのね?」
「えーと・・・、たぶん・・・」
晩ご飯の後の時間も、ぼくとアスカは、リビングで二人で過ごすことが多くなった。お茶とお菓子を持ち込んで、おしゃべりしたりする。もっぱら、アスカが話し掛けてきて、ぼくが答えてるだけなんだけどね。多分、今もアスカはリビングでテレビでも見ながら、お菓子の到着を待ってるはずだ。ミサトさん、いつも台所で仕事してるだけかと思ってたけど、気が付いてたのか。
「よし。じゃー、行くか」
「え? どこか行くんですか?」
◇
いろいろ乗せたお盆を持ってリビングに行ってみると、自分専用のクッションの上でひっくり返ってテレビを見てたアスカが、視線はテレビに向けたまま、
「遅かったじゃなーい」
と言った。
「あー、ごめんねー。あたしが引き止めちゃってさー」
ぼくの後ろから付いてきてたミサトさんが言った。アスカはずいぶんびっくりしたらしい。テレビの方に向けてた首を、ブンっ、とこっちに向けると、ぼくとミサトさんを交互に見やった。
ぼくがテーブルの上にお菓子やおつまみやグラスをセットしてる間に、ミサトさんはアスカの隣、テーブルの脇に、よいしょっ、と腰を降ろし、持ってたお湯割りを一口啜った。
「今日は仕事ないの?」
「ん? やっぱ、あたし、邪魔?」
ミサトさんが意地悪っぽく微笑んだ。
「邪魔だなんて言ってないじゃない」
「この時間いつも、あんたたち、ここで遊んでんでしょ?」
「別に遊んでなんかないわよ」
「ほんとー?」
「そりゃ、たまにゲームしたりはするけど・・・」
「ぼくが弱過ぎて相手にならないんですよ」
「へー」
「テレビ見たりしてるだけよ」
「そうなの?」
「マンガ読んだりすることもあるよね?」
「まあ、そうね。・・・で、何の用?」
「何よぅ、あたし、用がなきゃ来ちゃいけないの?」
「そうじゃないけど・・・」
「いっつも二人で楽しそうだからさー、今日はあたしも混ぜてよ。ダメ?」
ぼくとアスカは顔を見合わせた。
◇
そんなわけで、ぼくたちは今、三人で床に寝転んでババ抜きをしている。何故ババ抜きなのか、ぼくは良く分からないことにした。
アスカは、勝負事となると真剣だ。ミサトさんからカードを引くときは、カードを1枚ずつ摘まんでみては、ミサトさんの反応を窺ってる。ミサトさんの表情のどこを見て判断してるのかは分からないけど、なかなかジョーカーを引かない。たまにジョーカーを引くと、ミサトさんは大喜びするけど、アスカは顔色一つ変えない。ポーカー・フェイスだね。それとも、ババ抜きフェイスって言った方がいいのかな。
ぼくも、アスカの真似をして、表情を盗もうとするんだけど、アスカは全く顔色を変えないから、さっぱり分からない。それに、ぼくが何を引いても無反応。ぼくがジョーカーを引いちゃっても、喜んだりしないんだよね。いつもと全然違う。ぼくは、ちょっと、おかしくなって、クスっ、と笑ってしまった。それを見て、アスカは、少し、苦い顔をした。
「ははーん」
「何よ」
「てことは、ジョーカーはまだアスカね?」
「何で分かんの?」
「そりゃ分かるわよ。アスカはちっともうれしそうじゃないのに、シンちゃんうれしそうだもん」
そう言いながらミサトさんは、ぼくが今アスカから引いたばかりのジョーカーを引いていった。
「げっ」
「どうかしたの?」
「・・・あんたたち、二人してあたしをハメたわね?」
「そんなことしてませんよ」
「被害妄想じゃないの?」
「二対一なんて卑怯よ!」
「だからそんなことしてませんってば」
「そもそも組んだからって有利になったりしないじゃない。バカじゃないの?」
ミサトさんは、ムスっとした顔をして、アスカに手札を突き出した。
「それが二対一だ、って言うのに・・・」
不満たらたらのミサトさんの左手に握られた3枚のカードから、アスカは、見事にスペードのジャックを引き当てた。手札が空になって、ダントツの7勝目。
「またやられた・・・」
「アスカ強いね」
「関係ないわよ。こんなの運だけじゃない」
三人の真中に置かれてた、ネルフの2階の売店のコーヒー・チケットの最後の1枚は、アスカが摘まみ上げて、お財布の中にしまった。
「そうかなぁ。でも、結果はアスカの独り勝ちだよね」
「あんただって3回も勝ってんじゃないの」
結局1勝もできなかったにも関わらず、ミサトさんはすごくうれしそうだった。
「いいわねぇ・・・」
そう呟くと、もうすっかり冷めてしまったに違いない、四杯目の焼酎のお湯割りを、思い出したように飲み干した。
「何がですか?」
「・・・うん。なんていうか、頼もしくなったわ」
「アスカですか?」
「んーん。あんたたち二人」
ぼくとアスカは、顔を見合わせた。
「そう?」「そうですか?」
「そうよぅ。こう、アレよ、チーム・スピリット? みたいの感じんのよね」
「だから、組んでなんてないわよ」
アスカが抗議した。
「そういうことじゃなくって。今のあんた達、お互い、本当に信頼し合ってるでしょ? それがいいのよ」
「何言ってんのよ! 誰がこんなやつ、」
「えー、そうなの?」
「え?」
「だって、ぼくはけっこう信頼してるのに、」
「あ、ま、まあ、そうね、確かに、あたしも、信頼してないってわけじゃ、ないんだけど、」
ミサトさんが、あはは、と声を出して笑った。
「あんた達、一緒に住まわせて、ほんと、良かったわ」
「そう?」「そうですか?」
ミサトさんは、カードをまとめた中からジョーカーだけを取り出して、先にケースにしまった。
「うん。正直、こんなにうまくいくと思わなかった」
ミサトさんがカードをシャッフルする手元は、少し覚束ない。だいぶ酔っ払ってるみたいだ。でも、何かマジメな話をしようとしてるのかもしれない、と思った。
「現場で最後に物を言うのは、やっぱり、仲間を思い遣る気持ちだと思うのよ、あたしは」
「命令じゃなくて?」
「うん、もちろん命令も大事だけど、それを遂行してく上での、判断とか、気配りとか、気力の部分? そういうので、やっぱ、結果は違ってくると思うのよね。・・・もちろん、一人一人の力は大事よ。でも、あんたたち、今なら、お互いのために頑張れるでしょ? あたし、そういうふうになって欲しかったのよね」
ミサトさんは、苦労してシャッフルしたカードを、ケースに戻そうとしているが、なかなかうまく入らない。
「酔っ払ってんじゃないの?」
「うーん。シンちゃん、しまっといて」
ミサトさんは、カードとケースをぼくの方に押しやった。
「はい」
「あー、楽しかった。たまにはみんなで遊ぶのもいいわねー」
そう言うと、ミサトさんは、立てていた肘を寝かせ、腕に顎を乗せると、目を閉じた。
「ちょっと、そんなとこで寝るつもり?」
「寝ないわよぅ」
そう言いながらも、体を横向けにして、寝やすい体勢を探ってる。枕にした腕が、お菓子を入れたお皿に軽く当たって、チョコの包みが2つ、床にこぼれた。
「何よ! 寝る気満々じゃないの!」
そう言いながら、アスカが膝立ちになって、お菓子のお皿と、ウーロン茶の入ったグラスを、テーブルの上に避難させた。
「お寝みですよね。お部屋に行きましょう」
ぼくも立ち上がって、ミサトさんを助け起こそうとした。
「んー。今日は独りで寝るのヤだなぁ・・・。シンちゃーん」
「何ですか?」
「一緒に寝ようよー」
「え? わっ!」
ミサトさんを助け起こそうとしてたぼくは、首の後ろに両手を回されて、凄い力で引き寄せられた。咄嗟に手を突いたけど、ミサトさんのおっぱいの上に、横から覆い被さるような格好になってしまった。首の後ろと背中にミサトさんの手が回されていて、起き上がれない。
「ちょっと何してんのよ!」
アスカがぼくの後ろに回って、腰に両腕を回して引き剥がしてくれた。
「あんたね! 何考えてんのよ!」
「やーねぇ。ほんの冗談じゃないの。なにムキになってんのよ」
「冗談ってレベルじゃなかったでしょーが! セクハラよ! セクハラ!」
アスカは後ろからぼくに抱きついたまま、ミサトさんに抗議した。もうぼくは、ミサトさんからは完全に引き離されてるんだけど、いつまた襲われるか分からないとでも言うように、しっかりと抱きかかえられてる。ちょっと、恥ずかしいような・・・。
「アスカー、いつまで抱きついてんのー?」
「え?」
アスカは、腕を放すと、ぼくを右側の廊下の方へ突き飛ばした。ぼくは、「ひゃあ」と、情けない声を上げて、つんのめってしまった。
「そんなに焼き餅焼かなくったっていいじゃないの」
「違うわよ!」
「違うのー?」
「当たり前でしょ!」
「そっかー。・・・まー、あんまり目の前でいちゃいちゃされると、あたしも気分悪いし、・・・運用上も問題出そうだし、・・・あんた達が今のままでいいなら、その方がいいっちゃいいんだけどね。・・・でも、・・・ふぁ・・・」
ミサトさんが、大きなあくびを一つした。
「タオルケット、持ってきてやんなさい」
アスカがぼくに言った。
「あたしは・・・、あんたたち、応援するわよ・・・」
アスカは、何か言い返そうとしたみたいだけど、結局、ふっ、と笑っただけだった。
半睡半醒のミサトさんの頭に枕をあてがい、腰から上にタオルケットを掛け、グラスやお皿を台所に運んだ。リビングの電気を消した頃には、ミサトさんはすっかり寝入って、軽くイビキをかいてた。
「あんたも今日は災難だったわね」
台所で洗い物を始めたとき、アスカが言った。
「あはは。・・・でも、ミサトさんがあんなふうになったの、初めて見たなぁ・・・」
「そうなの?」
「うん」
「ふうん・・・。じゃあ、さっきのはホントに、冗談だったのね」
「そりゃそうだよ。・・・でも、何で?」
「つまり、・・・あたしに止めさせて、そのことをからかおうって魂胆よ。誰も止める人がいなかったら、冗談じゃ済まないでしょ?」
「なるほど」
「あんた、ほんとは、ちょっと、うれしかったんじゃないの?」
「え? 何が?」
「抱きつかれてさ」
「あー。・・・ミサトさん、確かにキレイだとは思うけど、アスカだって、あの人がどんな人か、良く知ってるだろ?」
「でも、キレイなお姉さんに抱きつかれたら、ちょっとはうれしいんじゃないの?」
「それは、嫌われるよりはいいけど、ちょっと困るよ、やっぱり」
「・・・次に、ああいうことがあったときも、あたし、助けた方がいい?」
「うん、助けてよ」
そう言って、ぼくは、アスカが抱きついて助けてくれたことを思い出した。簡単に、「助けてよ」なんて、言っちゃったけど、悪かったかな。
「ほんと?」
「うん。自分だけじゃ抜け出せそうになかったし。ほんとに、ありがとう、なんか・・・」
「いいわよ。・・・そういうことなら、仕方ないわね」
アスカは、ふふん、と笑った。
ぼくが、洗い物を終えて、タオルで手を拭いていると、アスカが訊いた。
「もう寝る?」
「えーと、今何時?」
「10時半」
「そっか・・・。アスカは?」
「テレビ見よっかな」
「でも、リビングはミサトさんが、」
「あたし、ワンセグ持ってるから」
「あー、そうなんだ」
「一緒に見る?」
「うん」
「じゃあ、あんたの部屋でいい?」
「狭いよ?」
「知ってるわよ」
◇
アスカがぼくの部屋に入るのはこれが初めてじゃないだろうか。わりかしキレイじゃん、だってさ。二人でぼくのベッドの上に上がって、壁を背にして並んで座り、携帯テレビを点けた。アスカがリモコンを操作して、最近人気のあるらしいお笑い芸人のトーク番組に合わせた。
「こういう番組、字幕が出るからいいわよね」
アスカはそう言うと、間に置いたお盆の上から、お茶のペットボトルを取って、一口飲んだ。
「アスカでも、聞き取れないこと、あるの?」
「そりゃあるわよ。一応外国語なんだから」
「へー」
テレビの中の若手の芸人が、下品なネタで笑いを取っている。
「くっだらないわねぇ」
「そう思うんなら見なきゃいいのに」
「あんたはこういうの好きでしょ?」
「うーん。嫌いじゃないけど・・・」
「はっきりしないのねぇ」
「下品なのが好きってわけじゃないよ。でも、面白ければいいんじゃないの?」
ぼくたちは、暫くそうしてテレビを見ていたけど、やがて、アスカが口を開いた。
「さっき、ミサトが言ってたことだけど・・・」
珍しく口篭もった。
「うん。ミサトさん、たぶん、ぼくたちをからかうのが楽しいんじゃないかな」
「からかうっていうか、あたしたちが仲良くしてるの、ホントにうれしいみたいね。その話、しょっちゅうされるし」
「しょっちゅう?」
「・・・でもないけど、2回くらい」
「ぼくも、今日、『アスカと、最近どう?』みたいに言われた」
「やっぱり。・・・悪気じゃないのは分かるんだけどねー」
「・・・さっき、ミサトさん、すごく楽しそうだったよね」
「そうね」
「アスカはイヤかもしれないけど、ミサトさんが楽しいんだったら、ぼくは別にいいっていうか、」
「そうなの?」
「え? うん、だって、ぼくたち、仲いいのは、ほんとだしさ・・・。仲、いいよね?」
「まあ、そうねぇ」
「アスカとは、最初のとき、あんなふうだったから、うまくやってけるのかな、ってちょっと心配だったんだよね」
「それは、お互いさまよ」
「あはは、そっか・・・。だから、今、こうやって、けっこううまくいってるの、ちょっと、うれしいっていうか・・・」
「ふーん・・・。うれしいんだ・・・」
アスカは、独り言のように、言った。
「アスカは?」
「え? え?」
「ミサトさんにからかわれるの、イヤ?」
「ああ、それは、・・・イヤよ」
「やっぱり?」
「うん」
「そうだよね。ぼくも、アスカはイヤなんだろうな、って思って、」
「ちょ、ちょっと、イヤなのは、ミサトに言われるのが、ってことよ?」
「うん。でも、これからも、事ある毎に、からかわれたりするんじゃないかな、多分」
「そうねぇ・・・」
アスカは、少し、考え込むように下を向いた。
「仲悪いフリ、するか」
「えぇ?」
「ミサトがいるときは、リビングに集まるのはやめ」
アスカがこっちを向いて言った。
「えー・・・」
ぼくは、少し、残念な感じがした。
「この部屋でいいじゃない。ミサトに見つかんないように」
そういうことか。
「あー、なるほど。でも、ミサトさん、ときどき、ここ入ってくるよ?」
「そう? でも、用があるなら、晩ご飯のときに言うでしょ? 一緒に晩ご飯食べて、その後ここに来ることって、ある?」
「なるほど。それはないかも」
「じゃあ、サイン決めとくわよ」
ミサトさんに気付かれないようにするために、ぼくたちは取り決めをした。晩ご飯の後、アスカがぼくの部屋に来るときは、台所を出てくときに、右手で左の肩を触って、頭を左に傾げる仕草をする。肩が凝ったときの仕草だね。今までは大きなお皿にお菓子をまとめて乗せて、お茶も2リットルのペット・ボトルにグラスを二つというスタイルでリビングに持っていってたけど、それはやめて、一人分ずつのお皿と、一人分のペット・ボトルで、アスカの部屋に届ける。ぼくが台所を下がるときも、自分の分だけ持って行くようにする。ミサトさんには、別々に過ごすように見えるだろう。そうしておいて、準備ができたら、そっと、アスカを呼びに行く。
冷静に考えたら、そこまでしてアスカと一緒にやることなんてないんだけど。でも、独りでマンガ読んだりしてるのよりは、ずっと楽しいから、いっか。
◇
アスカも、たぶん、おんなじなんだろう。というのも、それからというもの、ほぼ毎晩、アスカはぼくの部屋に遊びに来たから。
別段、やることはそれまでと変わらない。テレビを見たり、マンガを読んだり、ぼくが持ってるテープを二人で聴いたり。いろいろ話もした。学校のことや友達のこと、ネルフやエヴァのこと。大声出したりしたら、ミサトさんに気付かれちゃうかもしれないから、ベッドの上で、肩がくっつくくらいの距離に座って、ひそひそ声で。ぼくの右隣は、アスカの指定席になっていった。
「まったく鈴原のバカ、思い出すだけでも腹の立つ・・・」
「トウジの悪口言わないでよ」
「なんでよっ!」
「しーーっ」
ぼくは、慌てて、口の前に左手の人差し指を立てて、静粛を促した。
「・・・なんでよ」
「最初の友達なんだよ、ぼくの」
「だからって、」
「うん、そうだけどさ・・・。でも、トウジもミサトさんと同じなんじゃないかって気がするんだよね。ぼくたちのこと、別に、悪く思ってるわけじゃないんだよ、たぶん」
「だからって、からかわれてていいわけ?」
「いや、そうじゃないけど・・・」
「だいたいアレはあんたが悪いんじゃない。教室の中に家庭のこと持ち込まないでよ」
「いや、でも、待たせちゃ悪いと思ったから・・・」
「だいたい、今日あんたが日直だってのはずっと前から分かってることじゃないの。どうしてあらかじめ計画しとかないのよ」
「ごめん・・・」
「・・・ま、あたしも忘れてたんだけどさ」
「でも、待っててくれて助かったよ」
「・・・よし、サイン決めるわよ」
アスカは、いろんなサインを決めて、ぼくが紙に書いていった。
「肩こった」のポーズ … 晩ご飯のあと、あんたの部屋に行くわよのサイン (アスカ専用)
「腰が張ってるなぁ」のポーズ … 少し遅くなるけど、一緒に帰ろうのサイン (シンジ専用)
「じゃあ、“今日は先に帰っててのサイン”もあった方が、」
「ダメ」
「えー、でも、帰りにトウジたちとゲーセン行ったりさ、」
「分かったわよ、しょうがないわねぇ」
左のくつ下がずり下がっちゃったのを直すポーズ … 今日は先に帰っててのサイン (シンジ専用)
「これ、ちょっと、かっこ悪いような・・・」
「そう思うんなら、やらなきゃいいじゃない」
「えー・・・」
口元に手を当ててセキばらい1回 … 却下のサイン
「そこまでした上に、却下されちゃうの??」
「そりゃ、そういうこともあるわよ」
同じくセキばらい2回 … 了解のサイン
「よかった」
「あー、でも、そうなると、これが要るわね」
シャツの胸のポケットに、シャーペンを差す … 晩ご飯のおかず何がいい?のサイン (シンジ専用)
「これ、いつ使うの?」
「あんたに一人で買い物行かれて、変なおかず買って来られたら困るでしょ?」
「なるほど・・・」
「“お肉のサイン”が要るわねー。どんなポーズにするか・・・」
「“お魚のサイン”は要らないの?」
「使わないサイン決めたってしょうがないじゃない」
「じゃ、晩ご飯のおかず訊く意味もないよね?」
「なるほど。あんた頭いいわね」
“晩ご飯のおかず何がいい?のサイン”に、取消線を引いた。
「“ありがとうのサイン”も作らない?」
「なんでよ。“ありがとう”くらい口で言えばいいじゃない」
「そうだけどさ、学校でお互いにお礼言ったりすると、ほら」
「あー、確かにねー。まったくこっちのガキ共はホントにレベルが低いっていうか、」
「ドイツではそうじゃないの?」
「え? うーん。まあ、似たようなもんか」
上を向いて、それから下を向く … ありがとうのサイン
ぼくがちょっとやってみる。
「練習?」
「うん。アスカもやんなよ」
「なんでよ」
「これはアスカのためのサインなんだからさ」
「えー? どうしてそうなんのよ」
「だって、アスカあんまりお礼言わないだろ?」
「そんなことないわよ。言うべきときは、ちゃんと言ってるじゃない」
「ほんと?」
「・・・確かに、サイン決めとけば、使うこともあるかもね」
「だろ?」
アスカは、天井を見て、それから俯いた。顔を見合わせて、笑った。
「それなら“ごめんなさいのサイン”も決めるわよ」
「それ必要?」
「あんたすぐ『ごめん』って言うでしょ?」
「あー、そうだね・・・」
「あれ、口癖になってんのよ。だから、本当に反省して、誠心誠意謝りたいときは、こっちのサイン使いなさい」
右手で、右のほっぺたをつつく … ごめんなさいのサイン (シンジ専用)
「やってごらんなさい」
ぼくは、アスカと少し体を離して、右手で自分の右のほっぺたをつついて見せた。
「そうじゃないわよ」
「え?」
「あたしのほっぺた」
「ああ。・・・ええ!?」
「なによ」
「いいの?」
「あんたが本当に謝りたいことがあるときは、そうしなさいってこと」
「なるほど・・・」
「ほら、練習しなさいよ」
アスカは、ぼくの右のふとももの上に左手を置いて、ぼくの方に体を寄せると、頭を壁から離して、首の後ろに隙間を作った。腰から上を、ぴったりと寄り添わせ、半分こっちを向いたアスカの顔は、ぼくのすぐ目の前だ。
「えっと、後ろから、ってこと?」
「前からじゃできないでしょ?」
ぼくは、ちょっとどきどきしながらも、右腕をアスカの首の後ろに回して、アスカの肩を抱くような姿勢になった。右手を、アスカの右肩の上から伸ばして、人差し指で、おそるおそる、ほんの軽く、ほっぺたに触れた。アスカは、にこっ、と笑って、
「よし。じゃあ、赦してあげる」
と言った。
「ごめん・・・」
「何が?」
「いや、なんとなく・・・」
「それがダメだって言ってんのよ」
「あ、そっか」
「本当に謝りたくなったら、今のをやんなさい。そしたら、話くらい聞いてあげるから」
「うん。分かった」
ぼくは、アスカの肩に回した腕をどうしたらいいのか良く分からず、そのままアスカをじっと見つめることしかできなかった。
「・・・なに?」
「い、いや・・・」
「あたしの顔、珍しい?」
「え? いや、えっと・・・」
「まー、気持ちは分かるけど、別に、いつだって見られるじゃない」
「うん、そうだよね・・・」
でも、アスカの顔を見ないならどこを見ればいいのか、良く分からなかった。
その日、アスカは、次世代半永久機関の基礎理論について説明してくれた。ミサトさんのお父さんが発明したものだそうだ。でも、ぼくは、ぴったり寄り添ったアスカの身体と、アスカの肩を抱いたままの自分の右手と、ぼくのふとももの上に置かれたままのアスカの左手のことで頭がいっぱいで、正直、上の空だった。
◇
日曜日の朝、たいてい、ミサトさんは起きてこない。ゆうべも、ミサトさんは明け方近くまで台所で呑みながら仕事をしてたらしく、今朝起きて台所に来てみたら、テーブルの上がぐちゃぐちゃだった。ぼくは、グラスやお皿を片付けて、朝食の準備をした。だいたいこんな感じだからもう慣れたけどね。
二人だけで朝食を済ませ、お掃除とお洗濯をした後、ミサトさんのお昼ご飯を用意して、それからどこかに遊びに行くのが通例だ。でも、今朝は雨が降ってたので、お洗濯とお出掛けは中止することにした。ぼくは、台所、リビング、廊下、玄関、と、順に掃除を済ませた。まだアスカがお風呂掃除をしてる最中で、ちょっと悪い気はしたんだけど、アスカに声だけ掛けて、自分の部屋に引っ込んだ。
ベッドの上にうつぶせに転がって、“ヤングエース”を読み始めた。先週買ったんだけど、まだ1ミリも読んでなかったんだよね。
平日は、朝起きたら朝食とおべんとの準備、学校やネルフにマンガは持ってけないし、帰ったらアスカと宿題と予習があって、それから、晩ご飯の支度。食べ終わったらベッドでアスカとおしゃべり。独りになる時間っていうと、アスカがお風呂に入ってるときくらい。ゆっくりマンガ読む時間ってないんだよね。
以前は、ときどきはアスカと一緒に読むこともあったけど、ここのところ、そういう雰囲気にならないことが多い。それは、それでもいいんだけど。・・・一緒に読んでても、アスカの興味のないページは飛ばされちゃうから関係ないか。
そうして、久しぶりの読書タイムを楽しんでいたら、襖が3回ノックされて、それから3回ノックされた。 “シ・ン・ジ、あ・け・て”。アスカだ。
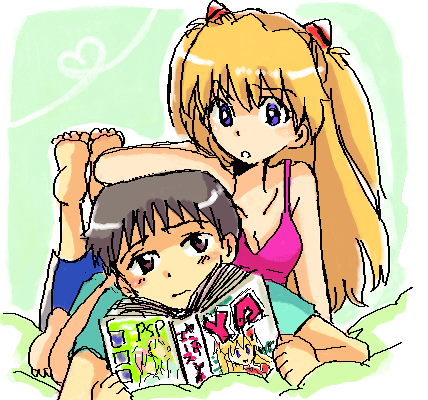 「入っていいよー」
「入っていいよー」
と言うが早いか、襖が開き、アスカが、するっ、と入ってきた。
「雨上がったわよ!」
後ろ手に襖を閉めると、少し抑えたトーンながらも、興奮気味に報告した。
「ほんと?」
ぼくの部屋には窓がない。
「ほら、そんなかっこしてないで、出掛けるわよ!」
ぼくは、読み掛けのマンガがもったいなくて、
「えー、でも、予報では、一日中ぐずついた天気だって・・・」
と、ささやかな抵抗を試みた。
「だから、止んでるときがチャンスでしょ? パッと行って、サッと買い物して、降りだす前に帰ればいいじゃない」
アスカは、ベッドに膝を乗せ、ぼくの腰の上に馬乗りになった。
「ほらー、なにぐずぐずしてんのよー。また降ってきちゃうでしょー?」
なんていうか、アスカの内股が腰のあたりに当たって、ちょっと、えっち・・・。
「これ、読み終わるまで待ってよ・・・」
というか、も少しこのままがいいな・・・。
「そんなの帰って来てからでいいじゃないの。ね? 後で一緒に読も」
「・・・今、一緒に読むのじゃダメ?」
「しょうがないわねー。なに読んでんの?」
アスカが右手をぼくの頭に乗せて、左の肩の上から覗き込んだ。
「“ヤングエース”なんて大して読むとこないじゃないの」
「でも、貞本義行が描いてるの、これだけだし、」
「あんた変態じゃないの? こんな腰の細い人間、実在するわけないじゃない」
「アスカだってこのくらいだろ?」
「あたしはもうちょっと太いわよ」
そう言ってから、アスカは、右手でぼくの脇腹を小突いた。
「あいっ」
「なに言わせんのよ」
「痛いよ」
「それより、今朝渡したサイン・リスト、覚えたの?」
そういえば、台所で朝食の準備してるとき、覚えとくように、って言われて、折りたたんだメモをもらったっけ。ちょっと変えた、って言ってたな。あのときは忙しくて読んでるヒマなかったし、その辺に置いといてうっかりミサトさんに見つかったらマズいと思って、エプロンのポケットに突っ込んだんだった。忘れてた。
「あー、えーと・・・」
「なによ、読んでないの?」
「ごめん・・・」
「まったく、マンガ読むより先にやることあんじゃないの」
「今晩、アスカが教えてくれるんだと思って・・・」
「だだだダメよ、ダメ! あれは、あんたが読んで、ちゃんと覚えなきゃダメなの!」
「そうなの?」
「そうよ」
ぼくは、観念した。
◇
ぼくたちは、着替えをして、駅前まで買い物に出掛けた。アスカが、台所のテーブルの上に、「シンジと駅前で買い物。1時までに戻る」と書いたメモを残しておいた。でも、買い物だけだし、たぶん、ミサトさんが起きる前に戻れるだろう。
“そごう”の隣の靴屋さんで、アスカは靴を買った。赤いヒールは、確かに、アスカに似合うな、とは思ったけど。「はい」って言いながら、その紙袋をぼくの方に突き出されてみると、少し抵抗したくもなる。
「似たような靴持ってるよね?」
「持ってないわよ」
「そうだっけ? あったと思うんだけど」
「ちょっと違うのよ。あんたには分かんないだろうけど」
「なんでだよ」
「いっつもおんなじエプロン使ってるからよ」
「だって、必要ないだろ?」
「それは、考え方の相違ね。立場が変われば、必要なものは変わるのよ」
「そうやってゴマカして」
「なによ」
「なんだよ」
「・・・ま、いいわ。折角お出掛けなのに、喧嘩したってしょうがないし」
なんでぼくが赦してもらう側になってるのか良く分からない。
「よし。あたしの買い物終わり」
3軒目の、“ユニクロ”を出た段階で、ぼくの両手には、紙袋が4つぶら下がっていた。
「次行くわよ」
「えー、今、終わり、って言ったんじゃ・・・」
アスカは、“生活雑貨のハイマート”にぼくを引っ張っていった。
アスカは、売り場の中をすたすたと歩いていく。ぼくは、持ってる荷物が、商品や、他のお客さんにぶつからないように、注意して歩かないといけない。待って、って言うのも何だか恥ずかしくて、とにかく一生懸命ついていく。すると、奥の売り場の、少し広くなったところで、アスカが立ち止まった。ぼくがようやく追いついたところで、並んでる商品の方に顎をしゃくって、
「ほら、好きなの選びなさい」
と言った。
「え?」
「荷物持ちのお礼に買ったげるから」
色とりどり、形もさまざまの、エプロンが並んでいた。
「い、いいよ、そんな・・・」
「ここまで来といてそれはないでしょ」
「アスカが連れて来たんだろ」
アスカは、ぼくを睨んだ。
「あっそう」
「あ、ごめん、えっと、そういうつもりじゃ・・・」
「あった方がいいんでしょ?」
「うん・・・。ありがとう」
「いくつ欲しいの?」
「え? いや、ひとつ、ひとつでいいよ、ほんとに」
「そう。・・・じゃ、これにしなさいよ」
アスカが、紺色の、撥水加工された、ロングのエプロンを指差した。 1,700円もする。
「こんな高いのじゃなくていいよ、そっちので」
「ポケットついてないじゃない」
「いや、ポケット、あんまり使わないし」
「おしゃれじゃないでしょ?」
「あ、そういう基準?」
「あたしが買ってあげんだから文句言わないの」
「・・・うん」
アスカは、レジで清算したエプロンを、ぼくの持ってる紙袋の一つに突っ込んだ。
「あんたに似合うわよ」
「そう?」
「たぶんね」
「エプロンが似合うのって、どうなのかな・・・」
「なに言ってんのよ。かっこいいじゃないの」
「そう?」
「そうよ」
ぼくは、少し、うれしかった。
「笑ってんじゃないわよ」
アスカが睨んだ。でも、口元が笑ってる。
「・・・ぼく、エプロンしてると、かっこいい?」
「うっさいわね! あたしに聞いてどーすんのよ! いいから次行くわよ!」
怒鳴られた。
「まだ何か買うの?」
「あんたは何か買わないの?」
こんなにいっぱい持ってたら、もう何も買えない。でも、アスカは、ぼくにお礼を買ってくれるために、荷物持ちさせたんだよね、たぶん。だって、いつもは、ぼくが重そうにしてたら、一つ二つ持ってくれるんだから。だから、それは言わないことにした。
「えっと、食材買わないといけないから、スーパー寄りたいんだけど」
「いいわよ」
「荷物が増えたら、1個だけ持ってくれる?」
「1個でも2個でも持ったげるから、好きなだけ買いなさいよ」
ぼくは、“ありがとうのサイン”をやってみせた。
「こんなところで使う必要ないじゃない」
そう言いながら、アスカは笑ってた。
ところが、スーパーに入って、フと、奥の方に掛かってる時計を見たら、もう12:30を回ってた。
「あ、時間」
「ん?」
「買い物してたら、間に合わなくなっちゃうよ」
ぼくたちは、第3新東京市の中なら自由に行動できるけど、所在は常にミサトさんに連絡していなければならない。 1時に戻る、って書いてきたから、それより遅くなるなら、電話しないと。
「いいわよ、少しくらい」
「でも、30分以上遅れちゃうんじゃないかな・・・。電話した方が、」
「まだ寝てるわよ、どうせ」
確かに、その可能性は高い。
「電話して起こしちゃったら、可哀想じゃない」
「それはそうかもね・・・。でも、いいのかなぁ・・・」
「シンジはマジメ過ぎんのよ。だいたい、理由、訊かれるわよ? 『アスカにエプロン買ってもらってました』って言うわけ?」
「それは・・・」
結局、ぼくが折れた。
◇
「「ただいまー」」
玄関を入って、声を揃えて帰宅の挨拶をすると、予想に反して、台所の方からミサトさんが姿を見せた。
「おかえんなさい。遅かったわねー」
確かに、1時半を少し回ってた。
「すみません、すぐお昼用意しますから」
「1時までに帰るって書いてあんじゃないの」
ミサトさんが、書き置きの紙をヒラヒラさせて、そう言った。
「細かいことグジグジ言うんじゃないわよ。いつもはまだ寝てんでしょーが」
「今日は早く起きたのよ」
アスカとミサトさんは言い合いながら、ぼくはそれを聞かされながら、台所に向かった。
ミサトさんは、台所のテーブルの自分の席に座り、ぼくは、テーブルの上に荷物をまとめた。アスカが、自分の買い物の紙袋を選び出して、自室へ行こうとしたとき、それまで黙っていたミサトさんが、声を掛けた。
「ちょっとあんたたち」
「なによ」「なんですか?」
「座んなさい」
アスカは、荷物を一旦テーブルの上に戻して、ミサトさんの隣の椅子に座った。ぼくも、食材の整理を中断して、ミサトさんの正面の席に座った。
「遅くなっても別にいいけど、連絡入れなさい」
「お小言?」
「そうよ」
「すみません」
ぼくは、謝ったけど、アスカは黙ったままだった。
「アスカ」
「なによ」
「あんたの身分は?」
「・・・エヴァンゲリオン弐号機専属パイロット」
「今、弐号機のレディネスは?」
「戦闘待機」
「戦闘待機のパイロットはどうすることになってるんでしたっけ?」
「・・・分かったわよ」
「あのねぇ、あんたたちには、あたしは何かと煙たい存在だってのは分かってんのよ。だから、いろいろいたずらすんのは別にいいわよ。でも、やるべきことはちゃんとやんなきゃダメよ」
「いたずらなんかしてないじゃない」
「そう?」
「そうよ」
「じゃあ、これなあに?」
ミサトさんは、メモ用紙を一枚、ヒラヒラさせた。それは、秘密のサイン・リストだった。
「ど、どこで・・・」
アスカは、そう言うと、ぼくの方を、キッ、と睨んだ。
「シンちゃんのエプロンのポッケ」
「勝手に探したの!?」
「なんでアスカが怒るわけ?」
「え? そ、そうだけど、でも、だって、ヒドいじゃないの!」
「パイロットが2名、30分以上も所在不明だったのよ? 事故かもしれない、誘拐かもしれない、その他のトラブルかもしれない。規則に従うなら、あたしは保安部に連絡しないといけないの。そうして欲しかったわけ? お買い物中に街中で確保されたかった? 家の中捜索して手掛かり探すのくらい、当然だと思わない?」
アスカは、黙った。
「あたしは別に、あんたたちがあたしに隠れてこそこそしてたことを怒ってるわけじゃないの。ほんとよ」
ミサトさんは、少し優しい口調になって言った。
「いつも言ってるけど、あんたたちの仲がいいのは、ホントに、・・・うれしいのよ。そうなれば当然、あたしを邪魔に感じることだってあるだろうって、そりゃ分かってるわよ」
「邪魔とか、そんなこと言ってないじゃない・・・」
「あらそう? じゃあ、見て見ぬフリしなくてもいいっての? 夜中にあたしに隠れていちゃいちゃしてんの、あたしが知らないと思ってんの?」
「い、いちゃいちゃなんてしてないわよ!」
アスカが、気色ばんで抗議した。
「そうですよ、そんな、ちょっと話したりしてるだけで、」
「すっとぼけたってダメよ。ほら、アスカ、最後のやつ、読んでみなさいよ」
ミサトさんが、秘密のサイン・リストを、アスカの目の前に突き出した。
「い、イヤよ!」
「あっそう」
ミサトさんは、メモを読み始めた。
「“後ろから、左手で、左のほっぺたに触る”は、」
「ちょっ、ちょっと! やめて!」
アスカが立ち上がって怒鳴った。
最後のやつっていうと、“ごめんなさいのサイン”か。右だったのを、左に変えたんだね。
「“バカミサトくたばれのサイン”だろうが何だろうが、決めたきゃ好きなだけ決めていいわよ。でも、それとこれとは別。あんたたちは、」
「分かったわよっ! もういいでしょっ!」
アスカは、そう叫ぶと、くるっ、と踵を返して、台所を出て行こうとした。
「アスカ!」
ぼくが呼び止めたけど、アスカは振り向かずに出てってしまった。
「あの、ぼく、アスカを、」
「ほっといてあげたら?」
「え?」
「アスカだって分かってんのよ。ただ、頭を冷やしたいだけでしょ」
ミサトさんがそう言った直後、玄関の自動扉が開いて、閉まる音がした。
「出てっちゃいましたけど・・・」
「あのバカ・・・」
ミサトさんは、がくっ、と項垂れた。
「やっぱ、ちょっち、やり過ぎたか・・・。まったく、扱い難いったら・・・」
ミサトさんは溜息をついて、それからこっちを向いた。
「悪いんだけど、アスカに、『ごめん』って、伝えてきてくんない?」
「はい」
ぼくも後を追いかけた。
◇
こうやってアスカを追い掛けるのは、これが二度目だ。前回は、確か、コンビニにいたんだっけ、と思って、まずはそこに向かうことにした。
マンションを出て、駅と反対方向へと走る。コンビニまでは、5分もかからない。しかし、外から見ても、アスカの姿は見えなかった。一応、中に入って、売り場の間の死角を探したけど、いなかった。となると・・・。
コンビニを出て、公園へと向かった。前回は、あそこでサンドイッチを食べながら頭を冷やしたんだった。入り口を入ると、デッキの手すりにもたれかかって、第3新東京市の街並みを見下ろしているアスカの姿が見えた。
「アスカ」
ぼくは近づいていって、声を掛けた。
「ミサトさんがさ、『ごめん』って伝えてって・・・」
「あんたもあんたよ」
アスカは、向こうを向いたまま言った。
「ご、ごめん・・・」
「何が?」
「え? えっと・・・」
今、ぼく、何を怒られたんだろう・・・。あ、そうだ。
「えっと、ミサトさんに言わせっぱなしで、アスカに味方できなくて、ごめん・・・」
「そうじゃないでしょ?」
「え?」
「悪いのはあたしだけなんだからさ、あんたはそう言えば良かったのよ」
「そんな・・・」
「恩を売っとこうってわけ?」
「違うよ、だって、ぼくにだって責任あるだろ? ・・・それに、アスカの味方、したかったんだよ、ホントに」
アスカは、何も言わない。
「ねえ、戻ろうよ」
こっちを向いてもくれない。
あ、そっか。サインだ。アスカ、「話くらいは聞いてあげる」って、言ってたじゃないか。
ぼくは、アスカの背後に立って、ほっぺたをつっつこうとして、さっきのやりとりを思い出した。 “ごめんなさいのサイン”は、左に変わったんだっけ。左手を伸ばし掛けて、ぼくはあることに気がついた。
もしもこれを、いつものベッドの上でやろうとしたらどうなるだろう。今みたいに、アスカが向こうを向いててくれれば簡単だ。でも、ぼくの右側に、ぴとっ、とくっついて、こっちを向いているアスカの左のほっぺたを、ぼくの左手で触るとしたら。身体を離して前から、っていう方法もあるけど、後ろから、だよね・・・。そ、それは、確かに、練習したりできない。できないよ!
 ぼくは、いけない想像を振り払うと、左手を伸ばして、アスカの左のほっぺたに、軽く、触れた。アスカは、ビクっ、と震えて、それからゆっくりとこっちを向いた。ぼくの左手を見て、それからぼくの顔を見て。でも、何も言ってくれない。
ぼくは、いけない想像を振り払うと、左手を伸ばして、アスカの左のほっぺたに、軽く、触れた。アスカは、ビクっ、と震えて、それからゆっくりとこっちを向いた。ぼくの左手を見て、それからぼくの顔を見て。でも、何も言ってくれない。
「あの・・・」
「・・・あんた、それ、本気なの?」
「え? ・・・うん」
「本当に?」
「うん・・・」
アスカは、おっかない顔をして、ぼくを睨んでいた。 “ごめんなさいのサイン”を繰り返すべきだろうか。しかし、この状態でそうするとなると、さっき想像した体勢にならざるを得ない。こんな、誰が見てるか分からないようなところじゃ、絶対、できない。誰も見てなくても、できないけどね。でも、それなら、どうしよう。ぼくは、どきどきして、口の中が乾いてきた。
アスカが、ふっ、と笑った。
「なによ、あんた、緊張してんの?」
「え? いや、あれ?」
ちょっと挙動不審だったかもしれない。
「そっか。本気なのね・・・。でも、何も、こんなタイミングじゃなくても、いいんじゃない?」
「そうなの?」
「ま、まあ、いいわ。じゃ、じゃあ、戻るわよ」
そう言うと、アスカは、ぼくの右腕に左手を絡めた。
「あ、え?」
「あんたが勇気出してくれたから、ご褒美。文句あんの?」
「いや、ないけど・・・」
ぼくたちは、腕を組んで、並んで歩いた。歩きながら、アスカは、一次方程式とグラフの関係について説明してくれた。ぼくにはその説明は良く分からなかったけど、アスカが何故そんな話をするのかは、なんとなく分かるような気がした。
◇
家に戻ると、アスカはミサトさんにちゃんと謝った。今後は、申告した予定と異なる行動を取るときは、ちゃんと連絡します、って。こんなふうに素直に謝るアスカを見たのは初めてだった。ぼくも一緒に謝った。
「まー、あたしも悪かったかな」
「いえ、ぼくたちが悪かったです。すみません・・・」
「んー。アスカ、ごめんなさいね」
「・・・いいわよ」
「よし、お昼ご飯にするかー。シンちゃん、今日は何?」
「えっと、朝のお味噌汁の残りがあるので、玉子入れてお雑炊にしようかと思って・・・」
「おー、いいわねー」
ぼくは、席を立って、エプロンを着けようとした。
「あ、待って」
アスカがぼくを遮った。
「新しいエプロン、着けてみなさいよ。・・・着けてみせてよ」
「今?」
「うん」
言うが早いか、アスカは紙袋をごそごそとやり始めた。
「なあに? 結局、エプロン、新調したの?」
「はい、アスカが買ってくれて・・・」
「あら」
ミサトさんは、アスカの方を向いたけど、アスカは気にせず紙袋をごそごそやっている。
「良かったじゃない」
ミサトさんが、優しく微笑んで、言った。
「ほら、これこれ」
アスカが、買ったばかりのエプロンを取り出した。ぼくは、それを受け取ると、ひとしきり眺めてから、肩紐に首を通した。腰紐を結ぼうと、手を後ろに回したら、
「貸しなさい。やったげるから」
と言って、アスカが膝立ちになった。
「自分でできるよ」
「いいから」
両腕をぼくの背中に回して、紐を交差させ、身体の前に回して、お腹の前で結ぶ。なんだか、母さんに服を着せてもらってるみたいで、ちょっと恥ずかしい。紐を結んだアスカが、立ち上がって、ぼくの姿を上から下まで眺め回した。
「かっこいいじゃない」
「そうかな・・・」
「ね、ミサト、ほら」
アスカが、ぼくの肩に手を掛けて、ミサトさんの方に向き直らせた。
「それを買ってて遅くなったわけ?」
「そうよ」「はい」
ミサトさんは、クスっ、と笑った。
「うん。似合うわねー。・・・怖いくらい」
ぼくはアスカの方を見て、お礼を言った。
「ありがとう」
「いいわよ。・・・そのうち、あたしにも、何か買ってね」
「うん。欲しいもの、考えといて」
「・・・シンジが考えてよ」
アスカは、下を向いて、小さな声で言った。
なんだか、急にかわいくなった気がした。
◇
お昼ご飯の後、アスカは、お買い物の整理をすると言って、部屋に戻っていった。ぼくも、後片付けを終えて下がろうとしたとき、ミサトさんから、最新のサイン・リストを返してもらった。
「でも、こんなの必要?」
「ええっと・・・、学校では、けっこう、重宝します」
「なるほどね」
返してもらったそのリストを、何の気無しに眺めた。リストの最後の方に、あんまり上手とは言えない字で、いくつか、サインが追加になっている。ふーん・・・。読み進めていって、ぼくは、重大な誤解に気付いた。
晩ご飯のとき、シンジの右肩にさわりながら、「ごちそうさま」って言う … 後でアイス持って来てのサイン (アスカ専用)
腕組みをして、「あたし先に帰るわよ」って言う … そんな連中ほっといて、今すぐ一緒に帰るわよのサイン (アスカ専用)
後ろから、左手で、左のほっぺたにさわる … 愛してるのサイン (シンジ専用)
ないとシンジが困るだろうから、決めておいてあげる
ただし、一生あたしの召使いとして尽くす覚悟ができたときだけ、使うこと
お昼ご飯を食べてるときに再び降り始めた雨は、既に本降りになっている。アスカは、部屋に篭ったまま、ずうっと出てこない。掃除機を掛ける音が聞こえてたから、掃除をしたんだろう。でも、掃除なら今朝もやったと思ったんだけど。その後も、どうも片付けか模様替えをしてるらしく、歩き回ったり物を動かしたりする音が聞こえている。その邪魔をするのも躊躇われて、自室のベッドに転がって、“ヤングエース”の続きを読み始めた。
◇
そして、どうやらぼくは、そのまま寝てしまったらしい。アスカに揺り起こされて気がついた。
「あれ? アスカ?」
「ごめんね、起こしちゃって」
「・・・今何時?」
ぼくは、上体を起こして、ベッドの上に座り直した。
「5時」
「えー、そんなに寝てたのか」
「疲れたんでしょ? お掃除して、お買い物だったし」
「そうかも」
「勝手に入ってごめんね」
「あ、そういえばそうだね。・・・何か、用?」
「うん。・・・ね、ちょっと、こっち来てよ」
ぼくはアスカに引っ張られるままに起き上がり、部屋を連れ出された。アスカは、ぼくの部屋の向かいにあるアスカの部屋の襖を開けると、先に入り、ぼくを招き入れた。
「入って」
この部屋に入るのは、アスカが引っ越してきたときに、荷解きの手伝いをして以来だ。入った途端、いい香りがした。でも、ちょっと強烈な気がするんだけど・・・。アスカは、ぼくが鼻をひくひくさせてるのに気がついたみたいだ。
「あ、あのね、香水の瓶、ひっくり返しちゃって、それでなのよ」
アスカは、ペロっ、と舌を出した。
「香水使うんだ」
「うん。持ってないわけじゃないのよね」
部屋には、音量を絞って音楽が流れていた。この曲ならぼくも知ってる。“When I Fall In Love”だね。ビル・エヴァンス。どこから音がしているのかは良く分からなかったけど、たぶん、パソコンかな?そのパソコンの置かれた机にも、その隣の本箱にも、チリ一つついていない。
「ずいぶんキレイな部屋だね・・・」
「そう?」
「うん」
「実は、さっき、キレイにしたのよね」
「あ、そうだったんだ」
「うん。ね、こっち来て、座って」
アスカは、自分のベッドを指差した。いいのかな。一瞬躊躇ったけど、アスカがこっちを見て微笑んでるのを見たら、断るのもヘンな気がした。ぼくがベッドの端に腰掛けると、その右側に、アスカも座った。
こうしてぼくを部屋に入れたからには、アスカは、何かぼくに話があるんだろう。でも、アスカは、俯いたまま、何も言わない。ぼくの方も、アスカに話さないといけないことがある。それを話してもいいのか、それとも、アスカが口を開くのを待った方がいいのか、良く分からなかった。迷っていると、やがて、アスカが言った。
「公園での、ことなんだけど・・・」
「うん。実は、ぼくも、そのことで、ちょっと、話があって・・・」
「そうなの?」
顔を上げて、アスカが訊いた。
「うん」
ごめん、実は、と言い掛けて、ぼくは、サインを思い出した。おそるおそる、隣に座っているアスカの肩を抱いて、右のほっぺたを突っついた。
「ん? なに? なんか、謝りたいわけ?」
「うん」
「いいわよ。赦したげる」
「え? ほんと?」
「うん」
「でも、まだ、何も言ってないけど・・・」
「いいのよ。こういうふうになって、最初にあんたが真剣に謝りたいってことがあったら、たとえそれがどんなことでも、赦してあげよう、って、決めてたのよ」
「そうなんだ」
「うん。・・・実は、あたしも謝らなきゃなんないことがあるからなんだけどね。あんたが、赦してくれたらいいな、って思ってて・・・」
ぼくは、かえって言い出しづらくなってしまった。
曲が、“My Foolish Heart”に変わった。
「それで、なに? 謝りたいことって」
ぼくが、言葉に詰まっていたら、アスカが促した。
「いや、その・・・」
「言い難い?」
「うん・・・」
「赦したげる、って、言ってんじゃないの」
アスカは、そう言って微笑むと、ぼくを左の肘で軽く小突いた。
「そうなんだけどさ」
ぼくは、こういう展開になるとは予想してなくて、緊張してきた。アスカの方を見ないようにしながら、話し始めた。
「実は、・・・あの、公園のときさ、今朝貰ったリスト、読んでなかったんだよね・・・」
「そうなの?」
「うん」
「それで?」
アスカは、それが何を意味するか、理解していないようだった。ぼくは、顔を上げて、説明しようとした。
「つまり、あの、」
その瞬間、アスカの顔色が変わった。
「ちょっと待ちなさいよ」
「うん」
「公園で、“愛してるのサイン”したわよね」
「いや、つまり、それ、間違いだったんだよね・・・」
アスカが、大きく息を吸い込んだ。
「どういうこと?」
「ほら、ミサトさんが、台所で、サイン、読んだだろ? 最後のサインって言うからさ、てっきり、“ごめんなさいのサイン”のことだと思っちゃってさ、あ、サイン、変わったんだな、って思って。だから、ホントは、“ごめんなさい”をしたかったんだよね・・・」
アスカは、口をポカンと開けて、ぼくを見ていた。
「ごめん・・・」
ぼくは、頭を下げた。すると、アスカの右手が伸びてきて、ぼくのポロシャツの胸倉を掴むと、凄い力で引っ張った。アスカは立ち上がり、ぼくも、よたよたと立ち上がった。
「や、やめてよ、」
「あんたね! やっていいことと悪いことがあるわよ!」
アスカは、ものすごい剣幕でぼくを睨んでる。
「さっき、赦してくれるって言ったじゃないか」
「その前提が成立してないじゃないの! あたしは、あたしのいない間にちょっと部屋を覗いちゃったとか、お風呂で裸覗いちゃったとか、そういうことだと思ったのよ!」
「そんなことしてないよ!」
「そっちの方がマシよ!」
「でも、だけど、だからって別に、アスカのことキライだとか言ってないだろ。なんでそんなに怒るんだよ」
アスカは手を放した。今それに気が付きました、とでも言うように、怖い顔が急に優しくなった。
「あ、なるほど。そういうこと?」
「え? え? どういうこと?」
「つまり・・・、あんた、どうなのよ、結局」
「何が?」
「だから、つまり、サインが間違ってた、ってのは、分かったわよ。それで・・・、つまり・・・」
アスカは、だんだんイライラしてきたみたいだった。ぼくは、この部屋の今の状況と併せて考えて、アスカが何を聞きたいのか、何となく分かった。でも・・・。
「ちょっと待ってよ。話が変だよ」
「なにがよ」
「だってさ、アスカは加持さんが好きなんだろ?」
アスカは、ぼくを睨んだまま、返事しなかった。「だからさ、ぼくがアスカのこと、・・・好きかどうかなんて、アスカに、関係ないだろ? 違うの?」
アスカは、何とも言えない目で、ぼくを見た。
「あんた、ほんとにバカね」
「なんでそうなるんだよ」
アスカは何か言おうとしてるようだったけど、なかなか次の言葉が出てこなかった。そして結局、
「出てって」
とだけ言って、ぼくを襖の方へと押しやった。
曲が、“Someday My Prince Will Come”に変わった。
◇
「えーーーー!! 修学旅行に行っちゃダメ!?」
「そ」
「どうして!」
「戦闘待機だもの」
「そんなの聞いてないわよっ!」
「今言ったわ」
あれから数日が経った。アスカはもう、晩ご飯のときに、肩が凝った仕草をすることはなくなった。今までは、ごちそうさまをしたら、とっとと台所を出てってたアスカだけど、このところ、そのまま台所にいて、みんなでお茶を、いや、ミサトさんはビールだけど、飲むことが多くなった。
今日も、そうしてるときに、修学旅行の話になった。アスカはずいぶん楽しみにしてたみたいで、ちょっと可哀想だな、とは思ったんだけど。
「誰が決めたのよっ!?」
「作戦担当の、あたしが決めたの」
ミサトさんの決め台詞だ。アスカは命令には逆らえない。そうなると、ぼくの出番になる。
「あんた! お茶なんか啜ってないで、ちょっと何か言ってやったらどうなの? 男でしょっ!?」
やっぱりね。でも、男かどうかなんて関係あるのかな。アスカ流に言うなら、ぼくは、男である前に、エヴァのパイロットなんじゃなかったっけ? 関係あるんだとしても、他のことならともかく、これはさすがに味方してはあげられない。
「いや、ぼくは、多分、こういうことになるんじゃないかと思って・・・」
「あきらめてたってワケ?」
「うん」
「ハッ! 情けない。飼い馴らされた男なんてサイッテー」
「そういう言い方はやめてよ」
アスカも、そろそろこういうことに慣れないと、この先ツラいと思うよ。
ミサトさんは、いい機会だから、ちょっとは勉強でもして、成績を上げるように、と諭した。でも、アスカはそれも気に入らないみたいだった。戦闘待機と違って、それは命令じゃないから、アスカも強気に言い返す。でも、いちいちミサトさんに切り返されると、とうとう癇癪を起こして出てってしまった。
ミサトさんは、少し、目で追ってたけど、やがて、ぼくの方に向き直った。
「何ですか?」
「うん・・・。最近、アスカと、どう?」
「どうって言われても・・・」
どう言ったものだろう。
「まあ、普通です」
「そう」
「はい」
「最近、アスカ、シンちゃんの部屋に入り浸ってないわよね」
「そうですね」
「喧嘩してんの?」
「いえ、そうじゃないですけど・・・」
「どっか、他所でデートしてるってこと?」
「そんなんじゃないですよ」
「ほんとに?」
「はい。あの、最近、そういうことは、しなくなりました・・・」
「そうなの。・・・もしかして、仲悪くなっちゃったの?」
「いえ、・・・以前ほど仲良くはないかもしれませんけど、でも、別に、喧嘩とかしてるわけじゃないですから。普通ですよ、普通」
「そう・・・」
ミサトさんは少し身を乗り出して訊いた。
「あたしのせい?」
「え!? いえ、違います、違いますよ」
「ほんと?」
「はい」
「そっか」
ちょっと、安心したみたいだった。
「アスカ、シンちゃんへの気持ち、冷めちゃったのかしらね・・・」
「え? いや、もともとそんなのないですよ? ただの友達っていうか、パイロット仲間ですよ」
「シンちゃん、そう思ってんの?」
「はい。いや、だって、間違いないですよ。こないだも、加持さんと一緒に水着買いに行ったみたいですし」
「・・・それ、なんでシンちゃんが知ってんの?」
「え? それは、アスカに自慢されましたから・・・」
「あー、そういうことか」
「はい」
ミサトさんは、缶ビールに手を伸ばして、一口呑んでから言った。
「アスカに、怒られたんだ」
言い当てられて、ぼくは、うろたえた。なんで分かるんだろう??
「えっと・・・」
「なるほどね」
ミサトさんは、微笑んだ。
「・・・アスカのこと、キライになった?」
「え? いや、そんなことないですよ」
「いざ、ってとき、アスカのこと、助けてくれる?」
「あ、はい。それは、まあ」
「作戦のときってことよ?」
「はい。だいじょぶです」
「アスカは、たぶん、これからも、シンちゃんのこと、からかったり、憎まれ口きいたりするだろうと思うけど、それでも、だいじょぶ?」
ミサトさんは、真面目に訊いてるみたいだった。ぼくも、持ってた湯飲みをテーブルに置いて、真面目に答えた。
「はい。それは、アスカは、ああいう性格だから、仕方ないんですよ。だから、だいじょぶです。大事な仲間ですから」
躊躇いなく答えたことに、自分でも驚いた。でも、本心だった。ああいうことがあったし、ちょっと険悪になることもあるけど、ぼくは別にアスカのことがキライなわけじゃない。作戦中にアスカが危ない目に遭うなんて、そんなこと考えたくないけど、もしそうなったら、って考えたら、やっぱり、答えは明らかだった。
Yes, I will.
「そう。・・・ありがと」
「いえ」
「問題はアスカねぇ・・・」
「そうなんですか?」
「うーん・・・。アスカ、シンちゃんのこと、助けてくれると思う?」
「さあ、それは・・・、本人に訊いてみて下さい」
「そうねぇ・・・。ま、今は触らないでおくか。逆効果でも困るしね」
そう言って、ミサトさんは、アスカが立ち去った方を見やった。
「アスカのこと、頼むわね」
「ええ・・・。えっと、でも、ぼく、何をすれば・・・」
「うん。そのときそのときで、シンちゃんにできることをしてあげて」
「はい、分かりました」
ミサトさんは、満足そうにうなずくと、缶ビールの残りを飲み干した。
ぼくは、良く意味が分からなかった。だけど、なんとなく、もやもやしてたことが、すっきりした気がした。
あとで、アスカに謝ろう。 “ごめんなさいのサイン”は、もう、できないけど、話くらい聞いてくれるだろ。
献呈の辞
じーまさん、2009年のおたんじょうび、おめでとうございます。
いつも仲良くしていただいてるお礼に、LASを贈らせていただきます。
舞台設定は、うちのサイト“のべるすけいぷ”で公開している “Concertino”
という作品の続篇ということになりますが、 “Concertino”を未読でも、問題なくお読みいただけると思います。
いっしょうけんめい書きましたので、楽しんでいただけたらうれしいです。
じーまさんの絵を、勝手に挿絵に使っちゃってごめんなさい。
次の一年も、楽しいこと、いっぱいあるといいですね。
そして、ステキな絵をいっぱい描いて下さったらうれしいです。
いく 拱手叩頭
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ななんなんと恐れながらも私のお誕生日祝いとして、いくさんからSSを戴いてしまいました!!ありがとうございますいくさん!!
ユニゾンを経て、心の距離がぐっと近くなったアスカとシンジ。
アスカの方はかなり積極的なのに、それに気づいてあげれないシンジの鈍さが歯がゆいというか可愛いというかww
ミサト交えてのトランプシーン、この会話のやりとりが何とも温かくてじんわりときました。
挿絵として入っている二つの絵は、なんの関連性もなく描いたものですが、このように一つの物語にすっぽりと組み込んで下さって、すごく嬉しかったです・・ww
マグダイバーへと続く少し前のお話。アスカとシンジの距離感が絶妙で萌えました!
本当にありがとうございましたwww
作者様への感想はコチラ↓

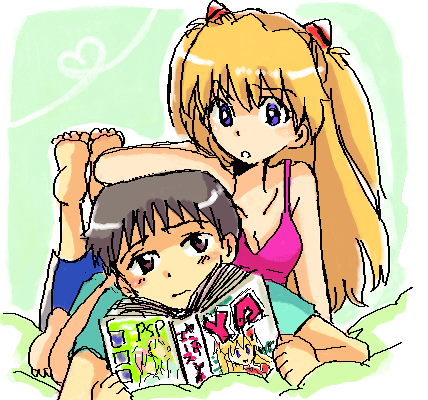 「入っていいよー」
「入っていいよー」 ぼくは、いけない想像を振り払うと、左手を伸ばして、アスカの左のほっぺたに、軽く、触れた。アスカは、ビクっ、と震えて、それからゆっくりとこっちを向いた。ぼくの左手を見て、それからぼくの顔を見て。でも、何も言ってくれない。
ぼくは、いけない想像を振り払うと、左手を伸ばして、アスカの左のほっぺたに、軽く、触れた。アスカは、ビクっ、と震えて、それからゆっくりとこっちを向いた。ぼくの左手を見て、それからぼくの顔を見て。でも、何も言ってくれない。